人生の折り返し地点といわれる40代。
高齢になった親の姿を身近で見て、「自分の老後の準備は大丈夫だろうか」「後悔のない人生を送れるだろうか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このような不安を解消するためには、40代のうちから少しずつ終活を始めるのが効果的です。この記事では、40代から終活を始めるメリットと、今のうちからやっておきたいことをわかりやすく解説します。一度きりの人生を後悔なく過ごすためのヒントが詰まっていますので、ぜひ最後までお読みください。
終活とは?
終活と聞いて、お墓や葬式の準備、財産の整理などを思い浮かべる人が多いでしょう。実は、終活は死後の準備をするだけではなく、後半の人生をより自分らしく生きるためのポジティブな活動でもあります。
終活の主な目的は次の通りです。
- 人生を振り返り、残りの時間をより充実させること
- 自分らしい最期を迎えるための準備をすること
- 残された家族の負担を軽減すること
この終活を通じて、人生を自分らしく、悔いの残らないものに近づけていけます。
40代から終活を始めるメリット
終活では老後や死後の準備、後半の人生をより良くするための活動など、やるべきことが多くあります。まだ若い40代のうちから始めれば、多くのメリットが得られます。その主なポイントを紹介します。
健康寿命まで時間の余裕がある
40代で終活を始める最大のメリットは、時間の余裕があることです。
厚生労働省が2022年にまとめた統計によると、日本人の平均健康寿命(日常生活に制限がない期間)は、男性が約72歳、女性が約75歳です。つまり、自分の意思でやりたいことを叶えられる年齢はこのくらいということになります。高齢になってから終活を始めた方がもっと早く始めればよかったと感じやすいのはこのためです。
その点、40代であれば健康寿命まで30年近く残されており、じっくりと準備を進められます。仕事や育児に多忙な年代ですが、時間をかけて試行錯誤できるからこそ、より納得のいく終活が可能です。
体力があるうちにいろんなことができる
老後になってからやりたいことを実現しようとしても、体力的に難しくなることがあります。40代のうちに終活を始めれば、未経験のスポーツにチャレンジしたり、海外旅行を楽しんだりと、体力が必要な夢も叶えやすくなります。
また、終活では不用品や思い出の品の整理などの体力を要する作業も多いです。高齢になってからでは負担が大きく、つい後回しにして家族に負担をかけてしまうこともあります。体力がある40代のうちから始めておけば、無理なくじぶんのぺ-スで進められます。さらに、必要なものを見極めて暮らす習慣がつき、不用品がたまりにくくなるメリットもあります。
判断力があるうちに重要なことを決めておける
40代はこれまでの人生経験や知識が備わっており、人生に関わる重要な判断に冷静かつ適切に対処できる年代です。
終活では、財産管理や相続、医療・介護の希望など、自分の将来を大きく左右する重要な決断が求められます。特に保険の見直しや相続の準備など、お金や財産に関する決めごとには、高い理解力と判断力が不可欠です。年齢を重ねるとどうしても判断力が衰えてくるため、人生の重要な選択を判断力がある40代のうちにしておくメリットは大きいです。40代のうちに重要な選択をしておけば、その後の生活環境や家族の事情が変わっても、冷静に見直して修正できます。より良い選択を柔軟に重ねられる点も、40代から終活を始めるメリットです。
早いうちに老後の不安を減らせる
老後に対する不安の多くは、お金と家族への負担に関するものです。40代のうちに終活を始めれば、このような不安を早い段階で軽くできます。お金の不安は、老後に必要な費用を具体的に試算し、準備計画を丁寧に見直すことで軽減できます。収入が安定し、人生経験も積んできた40代だからこそ、現実的で無理のない計画を立てられます。
また、相続や葬儀の方針、医療に関する希望を決めて、家族と共有しておくことも大切です。万が一のときの希望をあらかじめ伝えておけば、いざというときに家族が迷わずに行動できます。40代から準備を始めておくと、早いうちに老後の不安を減らせるだけでなく、家族にも安心してもらえるメリットがあります。
終活でやっておきたい8つのこと
ここでは、後悔のない人生と自分らしい締めくくりを実現するために40代から始めておきたいことを紹介します。自分のペースで無理なく進めるのがポイントです。順に見ていきましょう。
エンディングノートを作成する
エンディングノートは医療や葬儀、自分が亡くなった後の手続きなど、将来に関する希望をまとめておくものです。書いた内容と保管場所を家族と共有しておけば、いざというときに家族が落ち着いて対応できるので安心です。
エンディングノートの種類は市販のノートタイプや、スマホやパソコンで管理できるデジタルタイプがあり、自分で自由に作ることも可能です。ノートには次のような項目を中心に書きます。
- 基本情報
- 財産・契約関係
- 医療・介護の希望
- 葬儀・お墓の希望
- 相続・遺言の方針
- 家族へのメッセージ
エンディングノートには法的な効力はありませんが、自分の意思を家族に伝えるための大切な記録です。家族が読みやすく、定期的に更新しやすい形で作成することをおすすめします。
後半の人生プランを立てる
人生を後悔のないものにするためには、自分の理想を明確にしたプランが必要です。大切にしたい価値観や幸せを感じる瞬間を見つめ直し、どんな人生を送りたいのかを具体的に描くことが大切です。
後半の人生プランを立てるステップは以下の通りです。
- 現状を整理する:仕事・家計・健康など、今の暮らしを客観的に把握する。
- 理想を描く:どこで・誰と・どんな暮らしをしたいかを具体的にイメージする。
- 優先順位を決める:大切にしたいこと(家族・趣味・仕事など)を明確にする。
- 資金と準備を整える:必要な費用を見積もり、貯蓄や働き方を見直す。
- 健康を維持する:定期的な運動や検診を習慣化する。
- 家族と共有する:将来の希望を話し合い、計画をすり合わせる。
このような流れで行動計画を立てると、後半の人生を自分らしく、より理想的に過ごせます。
「死ぬまでにやりたいことリスト」を作る
人生を振り返ったときにやり残したことを後悔しないためには、「死ぬまでにやりたいことリスト」を活用するのがおすすめです。このリストを作成して行動すれば、限られた時間の中で大切なことから実現していけます。
リストは次のような流れで作成すると行動に移しやすいです。
- 思いつくままに書き出す:叶うかどうかは気にせず、やりたいことを自由に書き出す。
- ジャンル別に整理する:旅行・健康・趣味・家族・仕事・学びなど、テーマごとに分類する。
- 優先順位をつける:年代ごとの体力や行動力を考慮して、実現時期や重要度で分ける。
- 行動に落とし込む:実現したい項目を選び、いつ・どこで・どのようにといった実際の行動計画を立てる。
- 定期的に見直す:年始や誕生日など、ライフステージや気持ちの変化に合わせて更新する。
体力や行動力がある40代のうちに作成しておけば、より多くの夢を叶えられ、人生の満足度を高められます。
葬儀やお墓の希望を明確にする
自分らしい人生の締めくくりを実現するために、葬儀やお墓の具体的な希望を明確にします。希望内容を家族と共有しておけば、家族の負担が減り、安心です。
葬儀やお墓の準備のステップは次の通りです。
- 情報を集める:家族葬・永代供養など、さまざまな形式の特徴や費用を調べて比較する。
- 自分の希望を書きだす:葬儀の形式や埋葬方法などを具体的にメモする。
- 家族の意見を聞く:家族の考えや負担を考慮し、現実的に実現できる形を一緒に話し合う。
- お墓を検討・契約する:お墓を検討し、納得できる場所があれば契約する。
- 希望をまとめて記録する:エンディングノートなどに希望内容を明記する。
- 葬儀の希望をときどき見直す:家族構成や考え方の変化に合わせて更新する。
近年、葬儀やお墓の形は多様化しており、選択肢が増えている今だからこそ、自分の希望や家族の意向を明確にしておくことがますます重要です。
自分らしい人生の締めくくりを実現し、家族の負担を軽くするためにも、具体的な希望を共有しておくと安心です。
病気・介護に備える
病気になったり介護が必要になった場合の方針を具体的に決めて、家族と共有しておきます。万が一のときの希望や方針を決めておけば、自分が判断力を失った場合でも、家族が迷わずに対応できます。
病気や介護に備えて、次のような項目をあらかじめ考えておくと安心です。
- 延命治療の希望:どの程度の医療行為まで望むか。
- 臓器提供の意思:提供を希望するかどうか、希望する場合は範囲も明記する。
- 治療・入院に関する希望:どの病院や医師にお願いしたいか、在宅治療を希望するか。
- 介護サービスの利用方針:訪問介護・デイサービスなど、どの形を希望するか。
- 介護施設の希望:自宅介護か施設入所か、希望する施設の種類を明確にする。
- 費用の準備:医療・介護にかかる費用の目安を把握し、支払方法を家族と共有する。
財産の整理
財産の整理は、残された家族の負担を大きく減らし、家族間のトラブル防止にも役立ちます。所有状況や管理方法を明確にし、処分や相続の希望を整理しておくと安心です。
財産整理の具体的な行動ステップは次の通りです。
- 資産の全体を把握する:預貯金・不動産・保険・年金・証券・デジタル資産などを一覧にまとめる。
- 口座を整理する:口座を必要最小限に集約し、不要なものを解約する。
- 書類をまとめる:通帳、保険証書、契約書などを整理し、一か所に保管する。
- デジタル資産を管理する:ネットバンキング、電子マネー、サブスク、SNSのログイン情報などを一覧化する。
- 相続の方針を考える:誰に何を残したいか、どんな分け方が理想かを整理する。
- 遺言書を準備する:内容を弁護士や行政書士に相談し、法的に有効な形で作成・保管する。
- 家族と情報を共有する:相続方針や重要書類の保管場所、遺言書の有無を家族に伝えておく。
財産整理は40代のうちに完璧に仕上げる必要はありません。まずは、全体を把握することから始め、少しずつ整理・共有していくことが大切です。
物・デジタルデータの整理
整理されていない遺品の整理は、家族にとっても大きな負担になります。たまりがちな物やデジタルデータは、普段から整理することが大切です。本当に必要なものだけを残し、使わないものをためない習慣を身につけておくと、いざというときの整理もスムーズです。
普段から心掛けたい整理の方法は以下の通りです。
- 物の整理:衣類や家具、書類、思い出の品を「必要」「不要」「保留」に分け、使っていないものは早めに手放す。
- デジタルデータの整理:写真・動画・書類などをバックアップし、不要なデータは削除しておく。
- ログイン情報の管理:銀行・SNS・クラウドなどのIDやパスワードを一覧にまとめ、安全な場所に保管する。
- 不要な契約の解約:使っていないサブスクやオンラインサービスを解約する。
- 残したい情報の指定:家族に譲りたいデータや削除してほしい情報を明確にしておく。
- 家族への共有:データの保管場所や取り扱い方を家族に伝えておく。
人間関係の整理
人生を自分らしく理想的に過ごすためには、人間関係の整理も重要です。人間関係の整理は、無理に関係を切ることではなく、自分の時間と心を大切に使う考え方です。義理や形式的な付き合いを見直し、本当に大切な人とだけ過ごせば、日々の充実感や幸福度が高まります。
人間関係を見直すポイントを紹介します。
- 一緒にいて心地よいか:会ったあとに安心感や前向きな気持ちが残る相手を大切にする。
- 無理を感じていないか:相手に合わせすぎて疲れる関係は、少し距離を置いてみる。
- 信頼できる関係か:困ったときや悩んだときに、支え合える関係であるかを考える。
- 時間の使い方が自分らしいか:義理や惰性で続けている付き合いは見直す。
- 感謝や尊敬をもてるか:相手から良い刺激や学びを感じられるかを意識する。
限りある時間を誰と過ごすかによって心が満たされ、より豊かな人生を送れます。
40代からの終活で後悔のない人生に
終活は老後の準備をするだけでなく、後半の人生をより自分らしく、豊かに過ごすための取り組みです。40代は体力と判断力が充実しており、将来への準備を始める絶好のタイミングといえます。一度きりの人生を後悔なく締めくくるためにも、早いうちから前向きに終活を進めていくことをおすすめします。最新の情報や制度を取り入れながら、自分らしい人生を追求してみてはいかがでしょうか。
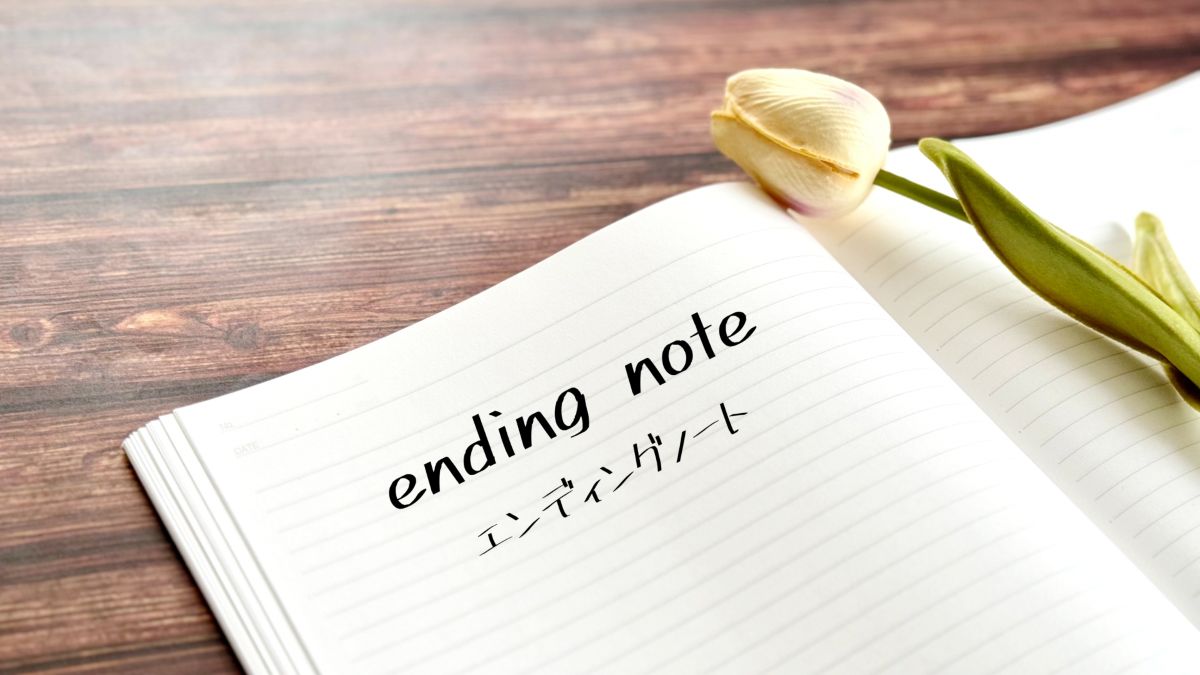
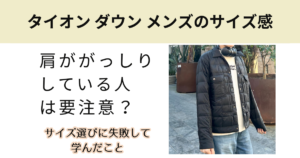

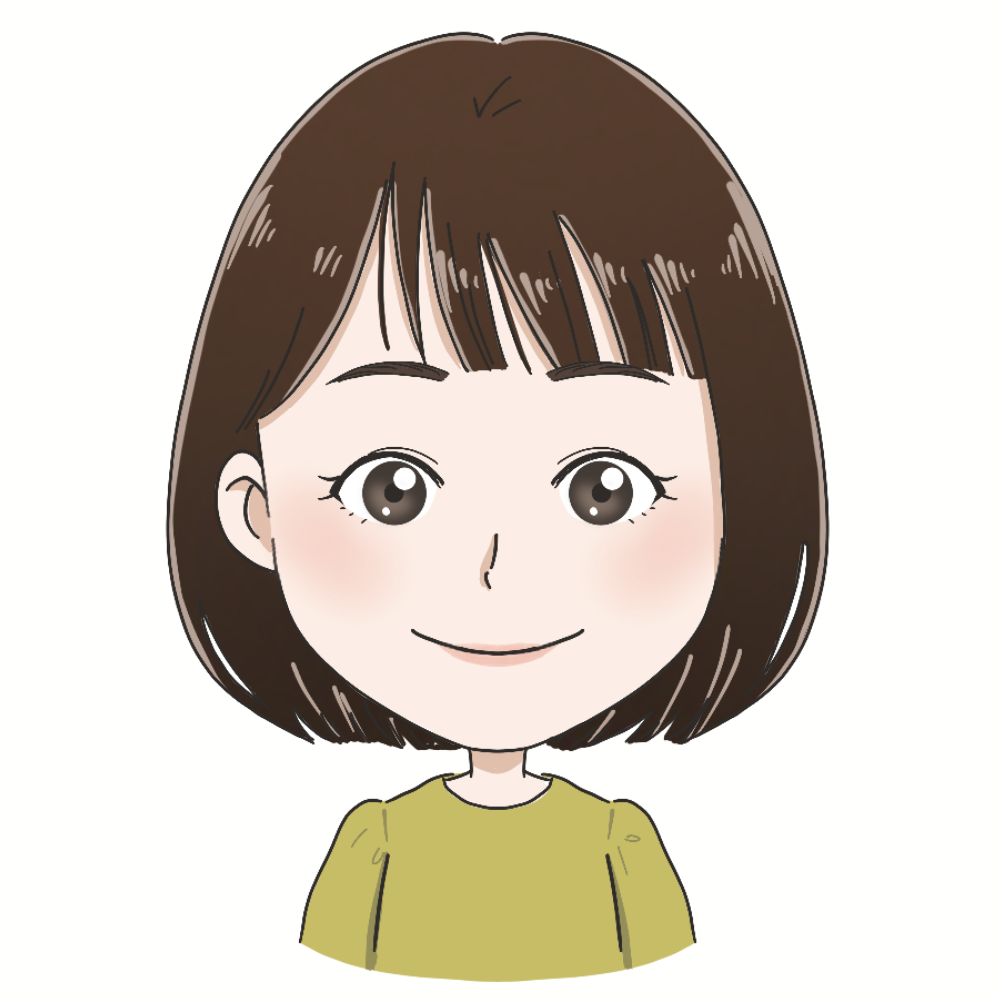
コメント